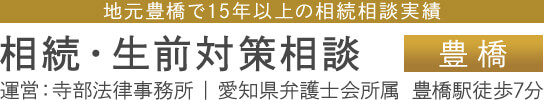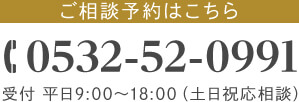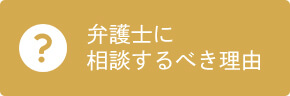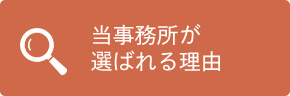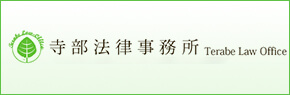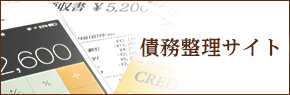特別受益に関する解説
特別受益
|
事務員:先生、遺産分割の事件で、特別受益(とくべつじゅえき)という言葉
を聞くことがあるのですが、これは何ですか。
弁護士:具体的な事例を仮定して説明します。
Aさんが、死亡し、法定相続人は、長男Bさんと、二男Cさんの2人であるとします。
そうすると、法定相続人は、Bさん2分の1、Cさん2分の1ですね。これが法定相続分です。
事務員:そうですね。
弁護士:Aさんには、遺言はなく、亡くなる1週間前まで、十分な判断能力があったものとします。
事務員:はい。
弁護士:例えば、Aさんの遺産が、預金だけで、1000万円であり、Bさんが、
Aさんの死亡する半年前にAさんから、200万円をもらっていると仮定します。 Cさんは、Aさんからは、何ももらっていません。
このときに、BさんとCさんが、1000万円を2等分して、
500万円ずつ分けることが公平でしょうか。
事務員:Bさんは、200万円をAさんの生前にもらっている(贈与されている)ので、
これだと、Bさんの方が200万円多くなると思います。
弁護士:民法は、特別受益(とくべつじゅえき)という制度を規定しています。
200万円の生前贈与が特別受益に該当するとすれば、1000万円に200万円を加えて、 2分の1ずつ分けるので、Cさんは、遺産から600万円、Bさんは、 遺産から400万円を取得することになります。Bさんは、 生前贈与で200万円を受け取っているので、遺産から400万円を受け取ることで 合計600万円を取得することになります。
事務員:なるほど、特別受益は、相続人の間の公平をはかる制度なのですね。
弁護士:もっとも、民法は、持戻し免除(もちもどしめんじょ)の意思表示(いしひょうじ)を
認めています。
事務員:持戻し免除の意思表示?
弁護士:先ほどの例で、遺産である1000万円に生前贈与の200万円を加えることを
持ち戻しということがありますが、Aさん(被相続人)が、持戻し免除の意思表示をしていると、 200万円を持ち戻すことなく計算をすることになります。 先ほどの例では、BさんとCさんが、500万円ずつ分けることになります。
事務員:持戻し免除の意思表示は、どのような場合に認められるのですか。
弁護士:例えば、持戻し免除の意思表示は、遺言で残すこともできます。
また、黙示でも認められる場合があります。
事務員:被相続人の意思が尊重されるのですね。
事務員:ところで、先ほどの例で、BさんとCさんの仲が良く、2人で話し合って、
法定相続分と異なる遺産分割をすることはできますか。
弁護士:通常、法定相続人で話し合いをして、
法定相続分と異なる遺産分割の合意をすることはできます。 また、財産がある場合でも、遺産の取得を希望しない場合には、法定相続人は 相続の放棄をすることもできます。
事務員:当事者の意思が大切なのですね。
|
|

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。