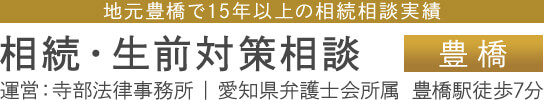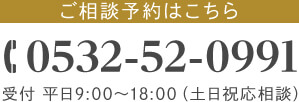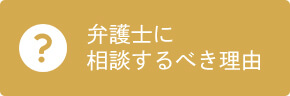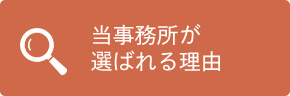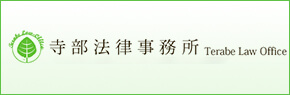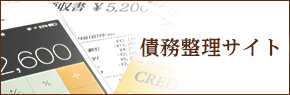【コラム】遺産分割後の不動産の共有と共有物分割
遺産分割後の不動産の共有と共有物分割 私の父は、昨年、死亡しました。私の父の法定相続人は、兄と妹である私です。 私の父の遺言は、ありません。 私の父の遺産は、ほとんどが自宅の土地、建物でした。 私は、兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまらず、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをしました。 遺産分割の調停が成立し、私... 続きはこちら≫
相続人の一部の相続放棄と債務の額
ご質問 私の父は、先月、死亡しました。 私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私、私の弟、私の妹の3人です。 私の父には、100万円ほどの預金と自動車がありますが、約300万円ほどの債務もあります。 私の父の相続に関し、私の弟、妹は、相続放棄する意向です。 私の弟、妹が相続放棄をした場合、私が相続する債務も... 続きはこちら≫
【Q&A】遺産相続により相続人の共有となった不動産と共有物分割請求の訴え
ご質問 私の父は、昨年死亡しました。 私の父の法定相続人は、私と私の弟です。私の父の遺言は、ありません。 私の父の遺産は、私の父が住んでいた土地、建物と預金です。 預金は、わずかな金額であり、遺産の大半は、土地、建物です。 私は、弟と遺産分割の協議をしましたが、まとまりませんでした。 私は、共有物分割の訴えという制度が... 続きはこちら≫
【コラム】終末期に望む治療の書面化
終末期に望む治療の書面化 最近、病院などで、希望する方が、リヴィングウウィルを作成する場合があるようです。 回復の見込みのない病気になり、死期が迫っている場合に、どのような治療を望むのか、ご本人が、意思を書面にする場合があります。 私は、現在の意思としては、回復の見込みがなく、死期が迫っているときには、苦... 続きはこちら≫
【コラム】相続税の節税目的の養子縁組みの効力
相続税の節税目的の養子縁組みの効力 相続税の節税を動機とする養子縁組は、効力を生じるのでしょうか。 民法802条1号は、養子縁組の無効原因の一つとして「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」を規定しており、相続税の節税を動機とする養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がないときに該当するのでしょう... 続きはこちら≫
「相続させる」旨の遺言の効力
「相続させる」旨の遺言の効力 実務上、遺言において、「相続させる」旨の文言が用いられる場合があります。 「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定、遺産の分割の方法の指定、遺贈のいずれにあたるのでしょうか。 「相続させる」旨の遺言は、どのように解釈したらよいのでしょうか。 この問題について、最高裁判所の裁判例では、 「「相... 続きはこちら≫
相続欠格と遺言書の破棄、隠匿
民法は、相続人の欠格事由を定めています。 民法891条5号は、相続人の欠格事由の一つとして、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、又は隠匿した者」をあげています。 それでは、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を 破棄又は隠匿した場合、常に相続人の欠格事由に該当するのでしょうか。 最高裁判所の裁判例では、... 続きはこちら≫
【コラム】預金口座の取引履歴の開示義務
預金口座の取引履歴の開示義務 一部の法定相続人が、被相続人の生前、被相続人名義の預金口座から、預金を引き出す場合があります。 このような場合、他の相続人が、銀行に対し、被相続人の預金口座の取引経過の開示を求める必要が生じる場合もあります。 被相続人の死亡後、法定相続人の一人が、銀行に対し、被相続人名義の預金口座の取引経... 続きはこちら≫
遺言執行者の選任
ご質問 私の母は、2ヶ月前に死亡しました。 私の母の法定相続人は、私と妹、弟です。 私の母は、自筆証書の遺言書を残してくれたのですが、遺言執行者の指定がありませんでした。 自筆証書遺言の検認の手続きは、先月、終わりました。自筆証書遺言の内容は、要約すると、銀行預金を私と妹にそれぞれ2分の1ずつ相続させること、自宅の土地... 続きはこちら≫
【コラム】遺産分割の対象と預金について、最高裁判所が判断を示しました
遺産分割の対象と預金について、最高裁判所が判断を示しました 銀行の預金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。 従前、最高裁判所は、可分債権の共同相続について、 「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承... 続きはこちら≫