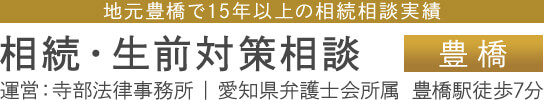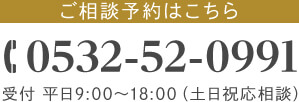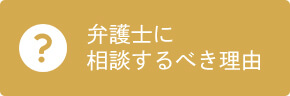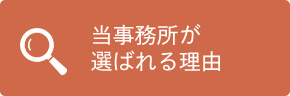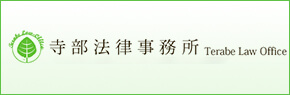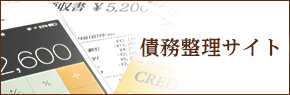遺産分割調停のポイント②遺言の有無
遺産分割調停のポイント②遺言の有無 遺産分割調停のポイントとして、ここでは、遺言の有無を取り上げます。 遺産分割調停においては、遺言の有無が問題となります。 遺言は、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。 公正証書遺言の有無は、被相続人の死亡後、法定相続人が、... 続きはこちら≫
遺産分割調停のポイント①相続人の範囲
遺産分割調停のポイント①相続人の範囲 ここでは、遺産分割調停のポイントについてご説明します。 このコラムでは、まず、相続人の範囲について説明します。 遺産分割の調停において、まず、相続人の範囲が問題となります。 相続人の範囲の問題は、大ざっぱに言えば、誰と誰の間で遺産を分割するかという問題です。 遺産分割の申立ての... 続きはこちら≫
相続予定だった預金を使い込まれた際の対応方法を弁護士が解説
被相続人の生前、預金が使い込まれていた場合 はじめに 被相続人の生前、被相続人と同居していた、あるいは、近くに住んでいた被相続人の子が、被相続人の預金を引き出すことはよくあることです。 また、被相続人が入院したり、施設に入所している場合に、被相続人の子が、被相続人の預貯金を管理することはよくあることです。 このような場... 続きはこちら≫
特別受益と死亡退職金
特別受益と死亡退職金 私の母は、公務員として働いており、半年ほど前に死亡しました。 私の母は、死亡時に現職の公務員でした。 私の母の遺言は、ありません。 私の母の法定相続人は、私の父、私の兄です。 私の母が死亡したことにより、配偶者である夫に死亡退職金約500万円が支給されます。 私の母の遺産は、預金であり、約5000... 続きはこちら≫
特別受益と結婚式の費用
特別受益と結婚式の費用 私の父は、昨年、死亡しました。 私の父の遺産は、預金だけです。 私の父は、遺言書を作成していませんでした。 私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と兄です。 私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、なかなかまとまりません。 私は、先日、特別受益という制度... 続きはこちら≫
特別受益と大学の学費
特別受益と大学の学費 私の母は、昨年死亡しました。 私の母の法定相続人は、私と兄です。 私の母の残した遺言は、ありません。 私の母の遺産は、預金だけであり、金額は、約5000万円です。 私の母は、私と兄が幼いころ、私と兄の父と死別し、その後、私と兄を育ててくれました。 私の母は、4年制大学を卒業後、公務員... 続きはこちら≫
推定相続人の死亡と遺言の効力
推定相続人の死亡と遺言の効力 1 はじめに 相続させる旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言の効力はどのようになるのでしょうか。 2 事例 次のような事例を仮定して説明します。 Aさんが、長男であるBさんに全部の遺産を相続させる旨の公正証書遺... 続きはこちら≫
【コラム】株式併合と遺産分割調停手続
株式併合と遺産分割調停手続 全国の証券取引所は、平成30年10月1日までに売買単位を100株に統一するための取り組みを進めています。 例えば、現在、売買単位が1000株となっている会社については、売買単位を100株にするためには、1単元の株式の数を1000株から100株に変更する場合や、1単元の株式の数を... 続きはこちら≫
【Q&A】相続開始後の寄与と寄与分
ご質問 私の父は、昨年、死亡しました。 私の父の遺産は、自宅の土地、建物、銀行預金、上場会社の株式、投資信託です。 私の父が残した遺言は、ありません。 私の父の法定相続人は、私と私の妹です。 私の母は、私の父の生前、私の父と離婚をしました。 私は、私の父の自宅の近くに自宅があり、私の妹は、結婚して遠方で生活しています。... 続きはこちら≫
【コラム】無権代理と相続 無権代理人が本人を相続した場合
法定相続情報証明制度 民法は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない旨規定しています。 無権代理行為に対し、一般に、本人は、追認をすることも追認を拒絶することもできます。 また、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明するこ... 続きはこちら≫