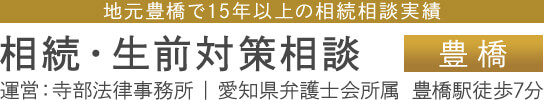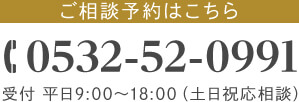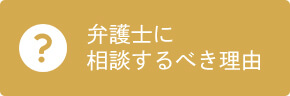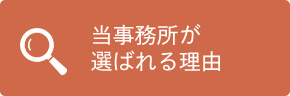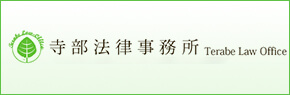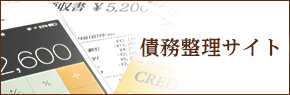【弁護士コラム】相続、寄与分と遺留分
相続、寄与分と遺留分
|
民法は、寄与分の規定を設けていますが、寄与分と遺留分は、どのような関係にあるのでしょうか。
民法1044条は、寄与分の規定を準用していません。民法の条文上は、他の共同相続人の遺留分を侵害する結果となる寄与分を裁判所が認定することは、妨げられないと考えられます。
もっとも、平成3年12月24日東京高裁決定は、「寄与分の制度は、相続人間の衡平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。しかし、民法が兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及び承継人に減殺請求権を認めている(1031条)。
|
 |
一方、寄与分について、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他の一切の事情を考慮して定める旨規定していること(904条の2第2項)を併せ考慮すれば、裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。」旨判示しています。
したがって、他の相続人の遺留分は、民法904条の2第2項の一切の事情のなかで考慮されると考えられます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。