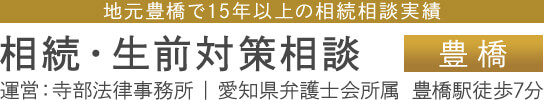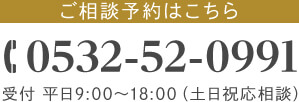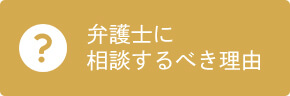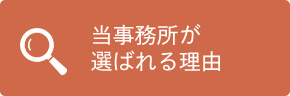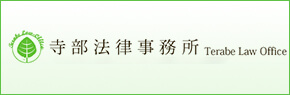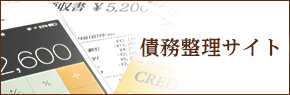子なし相続
近年、少子高齢化が進んでおり、子がいない夫婦も少なくありません。 被相続人(亡くなった方)に子がいない場合、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。 被相続人に父母がいれば、直系尊属として、法定相続人になります。 また、被相続人に父母、祖父母がいない(直系尊属がいない)場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉... 続きはこちら≫
遺留分権利者は、だれですか?
事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分権者は、誰ですか? 弁護士:遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人です。 事務員:相続欠格により、相続権を失った者は、どうなりますか? 弁護士:相続欠格により、相続権を失った者には、遺留分はありません。 もっとも、相続欠格の場合... 続きはこちら≫
老老相続
高齢化社会となり、被相続人の方がお亡くなりになった時点での年齢が高齢であり、相続人の方も高齢であるケースも少なくありません。 例えば、被相続人の方が亡くなった年齢が90代、相続人の方が70代ということもめずらしくありません。 遺言がない場合には、通常、相続人の方全員が遺産分割の協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産分... 続きはこちら≫
自筆証書遺言を法務局に預ける制度が令和2年7月10日から始まります
自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度が、令和2年7月10日から始まります。 自筆証書遺言とは、大ざっぱに言えば、手書きで書いた遺言書のことです。 今までは、法務局で自筆証書遺言を預かる制度はなく、紛失、隠匿、改ざんなどのおそれがありました。 この制度を利用すれば、自筆証書遺言の原本を法務局に預けることができます... 続きはこちら≫
相続債務がある場合に、遺留分は、どのように計算しますか?
事務員:遺留分侵害額を計算するにあたり、相続債務は、どのように影響しますか? 弁護士:相続人のうち、1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がある場合について、説明します。 弁護士:このようなケースについて、最高裁判所の裁判例があります。 事務員:はい。 弁護士:... 続きはこちら≫
遺留分侵害額とは、何ですか?
事務員:遺留分侵害額は、どのように計算するのですか? 弁護士:前回、遺留分額を説明しました。 事務員:そうですね。 弁護士:遺留分侵害額は、(遺留分額)―(遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額)―(民法第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定... 続きはこちら≫
遺留分額とは、何ですか?
事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分額は、どのように計算をするのですか? 弁護士:遺留分額は、 直系尊属のみが相続人である場合は、 (遺留分を算定するための財産の価額)÷3×(遺留分権利者の法定相続分) それ以外の場合 (遺留分を算定するための財産の価額)÷2×(遺留分権... 続きはこちら≫
遺留分侵害額請求権とは何ですか?
事務員:民法(相続法)改正前は、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利でしたが、相続法の改正により、どのような権利になったのですか? 弁護士:遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という名称になりました。 事務員:遺留分減殺請求権から、遺留分侵... 続きはこちら≫
再転相続における相続放棄の起算点について、最高裁判所の判決がありました
事務員:相続放棄は、いつまででもできるのですか? 弁護士:民法上、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」に行うことが必要です。 事務員:3カ月というと、意外に短いですね。 ところで、二次相続の場合は、どのようになるのでしょうか? 弁護士:令和元... 続きはこちら≫
特別寄与料は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:相続法の改正で、特別寄与料という制度が認められるようになったと聞きましたが、どのような場合に認められるのですか? 弁護士:特別寄与料請求権は、 ①相続人以外の被相続人の親族 (ただし、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者又は廃除によって相続権を失った者を除きます) ②無償で... 続きはこちら≫