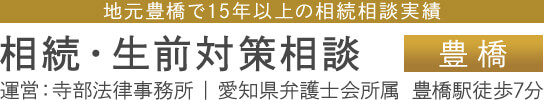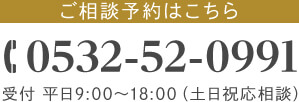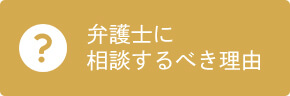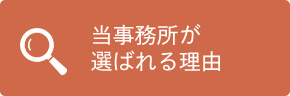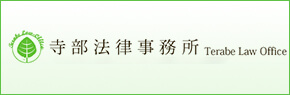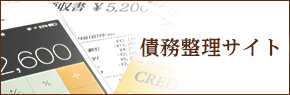【コラム】遺産分割の当事者
遺産分割の当事者
|
遺産分割の協議は、原則として、共同相続人全員で行います。民法は、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる旨規定しています。もっとも、民法は、被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる旨規定しています。 それでは、遺産分割の協議は、常に共同相続人全員でしなければならないのでしょうか。その一方、共同相続人以外の者は、遺産分割協議の当事者にならないのでしょうか。 |
 |
相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議の当事者にはなりません。相続放棄をしない場合、仮に、その者が取得する遺産が全くない場合でも、原則として、遺産分割協議の当事者になります。
相続分を譲渡した共同相続人は、遺産分割の協議に参加する必要はないと考えられます。一方、相続分の譲受人は、共同相続人でなくとも、遺産分割協議の当事者になると考えられます。また、包括受遺者は、遺産分割の当事者となると考えられます。
次に、遺産分割協議の当事者の一部を除外して遺産分割協議をした場合には、遺産分割の効力は、どうなるのでしょうか。
遺産分割の協議の当事者の一部を除外した遺産分割協議は、無効であり、除外された当事者は、遺産分割の再分割を求めることができると考えられます。
次に、法定相続人の1人が行方不明の場合、他の共同相続人は、遺産分割の協議を進めるためにどうしたらよいのでしょうか。
法定相続人の1人が行方不明の場合、他の共同相続人が家庭裁判所に対し、不在者の財産管理人の選任の申立をすることが通常であると思います。
なお、不在者の財産管理人は、民法103条に規定する権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可が必要となります。不在者の財産管理人は、遺産分割の協議の成立にあたり、家庭裁判所の許可が必要と考えられます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。