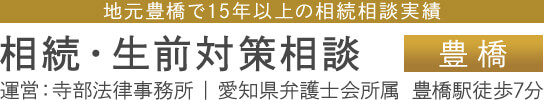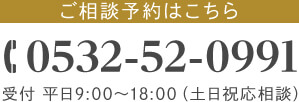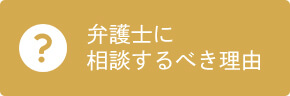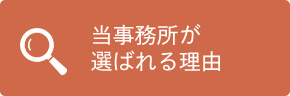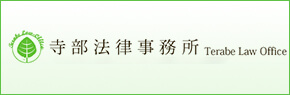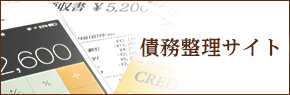相続と預金の使い込み(請求をする側から)①
事務員:相続事件において、相続人の一人の方が、亡くなった親の預金が思いのほか少ないという話を聞くことがあります。
弁護士:そうですね。
ここで、事例を仮定して考えてみましょう。
Aさんは、夫が先に死亡し、長男のBさん、Bさんの妻Cさんと一緒に生活していました。
Aさんが死亡し、法定相続人は、BさんとAさんの長女Dさんです。
Dさんが、Aさんの遺産を調べたところ、Aさんの生前、Aさんからは約2000万円の預金があると聞いていましたが、実際にAさん
の預金を調べてみると、Aさんの預金は、ほとんどありませんでした。その結果、Aさんの遺産は、ありません。
の預金を調べてみると、Aさんの預金は、ほとんどありませんでした。その結果、Aさんの遺産は、ありません。
弁護士:そこで、DさんがAさんの預金の取引履歴を取り寄せたところ、Aさんの死亡する1年前から、合計約2000万円が引き出されていたとします。
弁護士:この約2000万円をBさんが取得したと仮定します。
事務員:仮に、Bさんが、Aさんに無断で引き出した場合には、Dさんは、どのような主張をすることが考えられますか。
弁護士:この場合、Dさんとしては、法定相続分に相当する金銭の返還請求をすることを検討することになると思います。
事務員:どのような根拠に基づき、返還請求をするのですか。
弁護士:不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)または不法行為(ふほうこうい)に基づく損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)という法律構成をとることが多いと思います。
事務員:BさんがAさんに無断で引き出した事実を争って訴訟となった場合、ポイントとなるのは、何ですか。
弁護士:BさんがAさんに無断で引き出した事実をDさんが立証できるか否かがポイントになることが多いと思います。
続きは、別の機会に説明します。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。