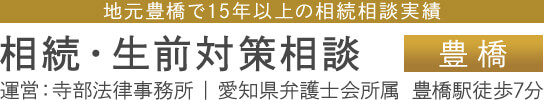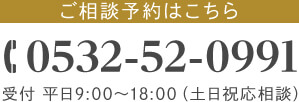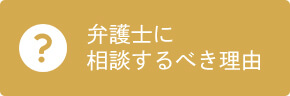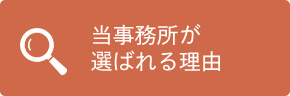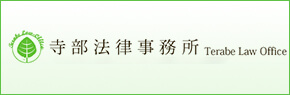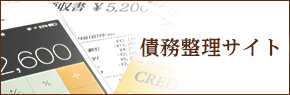相続人と連絡が取れない場合の対処法、手続きの進め方を 弁護士が解説
1 はじめに
被相続人が亡くなった場合、遺産の全てについて誰が相続するか明確に記載されている遺言があれば、通常、遺産分割をすることなく、遺言によって相続手続をすすめることができます。
遺言がない場合には、遺産分割をする必要があります。法定相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、通常、被相続人の預金の解約、名義変更、不動産の登記手続などができます。
それでは、相続人のなかに、連絡の取れない方がいる場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
2 法定相続人の確定
(1)法定相続人
遺産分割をするためには、法定相続人を確定する必要があります。
- ①配偶者は、常に相続人となります。
- ②被相続人の子は、第1順位の相続人となります。
被相続人の子が被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
代襲者が、相続の開始以前に死亡したときは、再代襲という制度があります。
- ③被相続人の直系尊属(父、母、祖父、祖母など)は、第2順位の相続人となります。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。
- ④被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹のうち、被相続人の相続開始以前に死亡していた者がいる場合には、その子(被相続人の甥、姪)が代襲して相続人となります。
(2)法定相続人の調査
まず、被相続人が生まれてから死亡するまでの間の連続した戸籍謄本等を取得します。
次に、上記の順位にしたがって法定相続人の有無を確認し、相続人の戸籍を取得します。
なお、遺産分割の交渉の代理、遺産分割調停の代理のご依頼を受けて、弁護士が、戸籍を取り寄せて、法定相続人を調査することもできます。
3 所在不明の相続人の調査
(1)はじめに
普段連絡を取っておらず、どこに住んでいるか分からない相続人がいる場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
(2)戸籍の付票の取得
所在不明の相続人については、戸籍の付票を取得します。
(3)遺産分割の協議
戸籍の付票の住所に手紙を送ることが多いと思います。
これに回答をしてくれれば、話し合いが進むことが多いと思います。
もっとも、手紙を送っても無視をされる場合もあると思います。
遺産分割の協議が進まない場合には、遺産分割の調停の申立を検討する場合が多いと思います。
(4)遺産分割の調停
遺産分割の調停を申立すると、調停期日が指定されます。
遺産分割の調停は、大雑把にいえば、家庭裁判所での遺産分割の話し合いの手続です。
遺産分割の調停を申し立てた方は、調停委員の先生を介して、当方の意向を相手方に伝えます。
相手方の意向は、調停委員の先生を介して、当方に伝わります。
遺産分割の調停について、弁護士に依頼をすると、弁護士は、遺産分割の調停申立書を作成し、裁判所に提出します。また、調停期日には、弁護士は、ご依頼者の方と一緒に出席し、必要に応じて意見を述べるなどします。
また、弁護士は、ご依頼者の方の言い分を確認し、必要に応じ、主張書面などの形式で書面を提出する場合があります。また、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、必要に応じて証拠を提出する場合があります。
遺産分割の調停において、合意に達すると、遺産分割の調停が成立します。調停調書に基づき、預金の解約や不動産の登記名義の変更などを行います。
遺産分割の調停手続について、合意に達する見込みがない場合などには、不成立となり、通常、遺産分割の審判手続に移行します。
(5)遺産分割の審判
遺産分割の審判期日においては、裁判官が、手続を進めます。
当事者の方は、必要に応じて、その主張を書面にて提出する場合があります。
当事者の方は、必要な証拠を提出する場合があります。
また、当事者の方は、裁判官から直接質問を受ける場合があります。
審判手続について、弁護士を依頼した場合、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、必要に応じて主張書面などの書面を提出します。
また、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、必要に応じて証拠を提出します。審判期日には、弁護士が出席します。ご依頼者の方の出席が必要な場合もあります。
審判手続について、審理を終結した後、審判がなされます。
審判が確定すると、審判書に基づき、預金の解約や登記名義の変更などの手続きを行います。
4 行方不明の場合
戸籍の付票を取得しても、職権で住所が削除されていたり、戸籍の付票の住所地に相手方が住んでおらず、どこに住んでいるか、行方不明という場合もあると思います。
このようなときには、どのようにしたらよいのでしょうか。
このような場合、不在者財産管理人の選任の申立をする場合があります。
従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、不在者財産管理人の選任などの処分をすることができます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存をしますが、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割等をすることができます。
不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人が遺産分割の協議や遺産分割の調停手続、審判手続に参加します。
不在者財産管理人は、法定相続分を下回る財産しか取得できない内容での遺産分割協議には、応じないことが通常だと思います。
5 まとめ
相続人のなかに行方不明の相続人がいる場合には、弁護士までご相談ください。