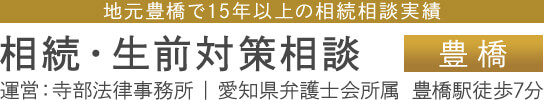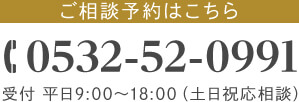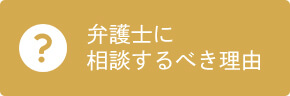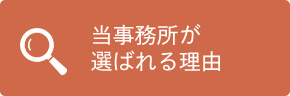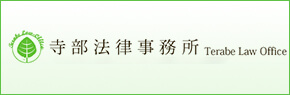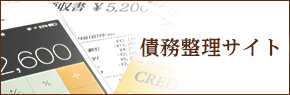遺産分割とは?手続きの流れや費用、注意点に関して弁護士が解説
1 遺産分割とは
(1)はじめに
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人の間で分けることをいいます。
遺言がある場合には、原則として、遺言に従って、被相続人の遺産を分けます。
遺言がない場合には、相続人の間で、遺産をどのように分けるか、話し合いをしたり、話し合いでまとまらないときなどには、家庭裁判所の調停、審判という手続を経て、遺産を分けます。
(2)遺産分割の方法
遺産の分け方には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の方法があります。
- ①現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、遺産そのものを分割する遺産分割の方法です。
例えば、土地を分筆して分割する場合や、Aという遺産を相続人甲が、Bという遺産を相続人乙が取得する場合などです。
現物分割は、遺産の現物を残すことができる方法ではありますが、被相続人の遺産の内容によっては、相続人間で公平に分けることが難しい場合があります。
- ②代償分割(だいしょうぶんかつ)
一部の相続人が遺産を取得し、その代償として、他の相続人に金銭を支払う遺産分割の方法です。
例えば、相続人の一人が不動産を取得して、他の相続人に代償金を支払う場合などです。
代償分割は、よく利用されている分割方法であり、金銭で調整するため、相続人間で、公平に分割することができる遺産分割の方法です。もっとも、遺産を取得する相続人が他の相続人に対して代償金を支払うだけの資力がない場合には、代償分割の方法をとることは難しいと思います。
- ③換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却して現金に換えて、その現金を相続人間で分ける分割方法です。
例えば、遺産である不動産を売却して、相続人間で金銭を分ける場合などです。
換価分割は、遺産を換金して金銭で分けますので、公平に分けることができる分割方法です。もっとも、遺産の換価に時間がかかったり、売却の費用などがかかる場合があります。
- ④共有分割(きょうゆうぶんかつ)
遺産を複数の相続人で共有する遺産分割の方法です。
例えば、土地を複数の相続人で共有して相続する場合などです。
共有分割は、遺産をそのままの形で残しつつ、相続人間の公平を実現することができる分割方法です。もっとも、遺産分割後に共有関係が残りますので、遺産分割が終わった後に、共有者間において、トラブルになる可能性があります。
2 遺産分割の手続の方法
(1)相続人の調査
ア 遺産分割の手続をするためには、誰が遺産分割の当事者になるのか、把握する必要があります。
そのため、相続人の調査をします。
イ 配偶者
配偶者は、常に相続人になります。
ウ 第1順位
第1順位の相続人は、被相続人の子です。
代襲相続、再代襲相続の規定があります。
エ 第2順位
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。
直系尊属の間では、親等の近い者が優先します。
オ 第3順位
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
代襲相続の規定があります。
カ 相続人の調査のためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの間の連続した戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を取得し、そこから、相続人を調査します。
(2)遺産の調査
遺産分割をするためには、何を分割するか、遺産分割の対象を明確にする必要があります。
不動産については、市区町村役場で名寄帳(なよせちょう)を取り寄せることが多いと思います。
銀行預金については、個別に金融機関にあたることが多いと思います。
株式については、相続人が、被相続人が取引している証券会社を知っている場合には、当該証券会社に問い合わせることが多いと思います。
取引をしている証券会社が分からない場合、証券保管振替機構(ほふり)に対し、登録済加入者情報の開示請求をすることが考えられます。しかし、登録済加入者情報では、口座を開設している口座管理機関の証券会社、信託銀行は分かりますが、銘柄名、取引履歴、株式数などは、分かりません。そこで、証券保管振替機構(ほふり)の情報などを参考にして、証券会社に残高の証明書の発行などを請求したりすることが考えられます。
保険については、相続人が、被相続人が保険契約をしている保険会社を知っている場合には、当該保険会社に問い合わせることが多いと思います。
保険契約をしている保険会社が分からない場合、生命保険契約照会制度、医療保障保険契約内容登録制度に基づく開示請求を一般社団法人生命保険協会に求めることが考えられます。もっとも、一般社団法人生命保険協会に加入していない保険会社については、個別に問い合わせる必要があります。
(3)相続の放棄・単純承認・限定承認
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に手続を行う必要があります。
限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申立をする必要があります。
相続の放棄、限定承認をしなければ、単純承認となります。
法律が定めた行為をすると、単純承認をしたものとみなされる場合がありますので、注意が必要です。
(4)遺産の分配、相続に伴う手続
遺言がある場合には、原則として、遺言に基づき遺産を分配します。
なお、法定相続人全員が合意した場合には、遺言の内容と異なる遺産分割をすることもできると考えられます。
遺言がない場合には、法定相続人全員で遺産分割の手続が必要になります。
遺産分割の協議をして、合意した場合には、遺産分割協議書を作成し、法定相続員全員が署名、実印を押印、印鑑証明書を添付することが通常です。
3 遺産分割にかかる費用
法律相談料
60分無料
相続人調査
3.3万円+取寄書類の通数×1000円+取寄実費
※通常の郵券は事務所負担です。
※遺産分割において、相続人調査を要する場合は相続人調査の手数料をご負担いただきます。
そのほかの料金に関しては以下の費用ページからご参照ください。
4 遺産分割を行う上での注意点
①相続人を確定する
遺産分割を行うには、相続人を確定することが大切だと思います。
遺産分割を行うには、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
法定相続人がもれていると、遺産分割の合意の効力が生じないので、注意が必要です。
②遺産を調査する
遺産をもれなく調査することが大切だと思います。
遺産の一部が漏れていると、再度、あたらに発見された遺産について、遺産分割をすることが必要になることがあります。
③遺産を適切に評価する
遺産を適切に評価しないと、遺産を公平に分割することができません。
遺産を適切に評価することは、遺産分割を行ううえで、重要であると思います。
④遺産分割の手続を行う
ア 遺産分割の協議
遺産分割については、協議(話し合い)から始めることが多いと思います。
遺産分割の協議(話し合い)が合意に達したときは、遺産分割協議書を作成します。
そのうえで、不動産の登記名義の変更、預金の解約等の手続をします。
イ 遺産分割の調停
遺産分割の協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をします。
遺産分割調停の申立をすると、家庭裁判所において、調停期日が開催されます。
調停期日においては、調停委員の先生を通じて、相手方に意向や主張を伝えます。
相手方の意向や主張は、調停委員の先生を通じて、伝わります。
当事者の方が、主張を記載した主張書面や証拠を提出する場合もあります。
当事者間で合意に達すると、調停調書が作成されます。
調停調書をもとに、不動産の登記名義の変更、預金の解約等の手続を行います。
ウ 遺産分割の審判
遺産分割の調停手続の期日を重ねても合意に達しない場合、裁判官の判断により遺産分割の審判手続に移行することが通常です。
遺産分割の審判期日は、裁判官が、期日を進行します。
当事者の方は、主張を主張書面にまとめて提出したり、証拠を提出したりします。
審理が終結すると、裁判所は、審判をします。
審判に対し、法律の定める規定に従い、不服申立をすることができます。
5 遺産分割を弁護士に依頼するメリット
①遺産分割の協議
弁護士は、ご依頼を受けると、相続関係を調査することが多いです。
遺産の調査については、当事務所では、ご依頼者の方にご説明をしたうえで、ご依頼者の方にお願いをしています。
弁護士は、ご依頼者の代理人として、他の相続人と遺産分割の協議をします。
②遺産分割の調停
遺産分割の調停のご依頼を受けると、弁護士は、代理人として、遺産分割の調停の申立書を家庭裁判所に提出します。
遺産分割の調停期日には、弁護士は、出席します。寺部法律事務所では、ご依頼者の方にも調停期日のご出席をお願いしています。
弁護士は、調停期日に出席し、法的な主張を述べたりします。
弁護士は、必要に応じて、主張書面を提出したり、証拠を提出したりします。
③遺産分割の審判
弁護士は、遺産分割の審判期日に出席をします。
弁護士は、必要に応じて、主張書面を提出したり、証拠を提出したりします。
④弁護士を依頼するメリット
遺産分割においては、特別受益、寄与分などの法的な主張がなされる場合があります。
また、遺産の評価、配偶者居住権など、遺産分割において、問題となりうる点は、多くあります。
遺産分割の調停や審判において、法的な主張を書面にまとめたり、必要な証拠を選んで提出する場合もあります。
このように、遺産分割の手続をすすめるためには、専門的な知識が必要になる場合が少なくありません。
相続に関する専門的な知識や調停、審判の経験を持った弁護士に依頼をすれば、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがいながら、調停や審判の手続において、必要な法的主張をしたり、証拠を選択したりします。
6 まとめ
遺産分割、相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。