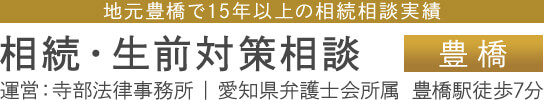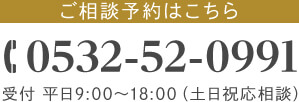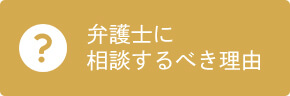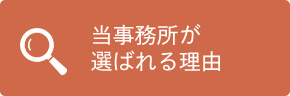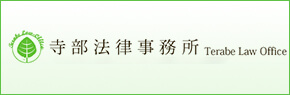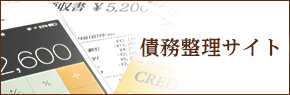遺留分侵害額請求とは?流れや計算方法を豊橋の弁護士が解説
1 遺留分侵害額請求ができる可能性がある方
(1)遺留分侵害額請求ができる可能性がある方は、兄弟姉妹以外の相続人です。
被相続人の兄弟姉妹の方は、相続人であっても、遺留分侵害額請求権は、認められていません。
(2)遺留分を侵害する遺言等があること
遺留分を侵害する遺言、遺贈、死因贈与、生前贈与などがあることが、遺留分侵害額請求をするために必要になります。
2 遺留分のご相談
「長男に全部相続させるという遺言がある」
「被相続人が亡くなる直前に、財産のほとんどが一人の相続人に贈与されていた」といったご相談を受けることがあります。
このような場合、遺留分侵害額請求をすることができる場合があります。
3 遺留分侵害額請求とは?
遺留分制度は、被相続人の遺産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を請求する金銭請求権をいいます。
4 遺留分侵害額請求をするためには
(1)遺留分侵害額請求ができる条件
①遺留分侵害額請求をすることができる方
兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺留分侵害額請求の権利者となる場合があります。
具体的には、配偶者は、常に相続人になります。
子は、第1順位の相続人になります。子については、代襲相続、再代襲相続という制度がありますので、例えば、子が被相続人よりも先に死亡していたときには、その子(被相続人の孫)が相続人になります。
直系尊属は、第2順位の相続人になります。
したがって、被相続人に子(代襲相続人、再代襲相続人を含む)がいないとき(第1順位の相続人がいないとき)に、直系尊属が相続人になります。
直系尊属の間では、親等の近い者が優先して相続人になります。
例えば、被相続人の父母が健在の場合、被相続人の祖父母は、相続人になりません。
②遺留分侵害額請求の相手方
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む)、受贈者など遺留分を侵害する行為によって直接利益を受けた者及びその包括承継人です。
遺留分侵害額請求の順序、割合についての説明は、ここでは、省略します。
(2)遺留分侵害額請求の計算方法
①まず、遺留分算定の基礎となる財産を計算します。
遺留分算定の基礎となる財産は、(被相続人が相続開始時に有していたプラスの財産の総額)+(遺留分算定の基礎となる財産に算入される生前贈与の価額)-(相続債務の額)により計算をします。
例えば、亡くなった方が、亡くなった時点において、1000万円の預金があり、亡くなる直前に相続人の一人に特別受益にあたる100万円を贈与し、亡くなった時点において、100万円の借金があった場合、遺留分算定の基礎となる財産は、1000万円+100万円-100万円=1000万円となります。
②次に、遺留分侵害請求権者の個別の遺留分率を計算します。
遺留分侵害請求権者の個別の遺留分率は、総体的遺留分の割合×法定相続分により計算をします。
例えば、亡くなった方の相続人が長男、二男の二人であり、亡くなった方が、長男に全ての財産を相続させる公正証書遺言を作成していた場合、二男の個別の遺留分率は、2分の1×2分の1=4分の1になります。
③次に、当該相続人の遺留分額を計算します。
遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産の額×個別の遺留分率で計算をします。
遺留分算定の基礎となる金額が1000万円である場合、亡くなった方の相続人が長男、二男の二人であり、亡くなった方が、長男に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していた場合、二男の遺留分額は、1000万円×4分の1=250万円になります。
④次に、遺留分侵害額請求額を計算します。
遺留分侵害額は、(遺留分権利者となる相続人の遺留分額)-(遺留分権利者が得た遺贈、特別受益の価額)-(遺産分割の対象となる財産がある場合、遺留分権利者の具体的相続分に相当する額)+(被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、民法899条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額)で計算をします。
例えば、亡くなった方の相続人が長男、二男の二人であり、亡くなった方が、長男に全ての財産を相続させる公正証書遺言を作成していた場合、二男の遺留分額が250万円、二男が遺贈や特別受益となる贈与を受けておらず、亡くなった方に債務がない場合、二男の遺留分侵害額請求の金額は、250万円となります。
5 遺留分侵害額請求は、いつまで請求できる?(遺留分と消滅時効)
(1)短期消滅時効
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求権を行使したことによって生じた請求権は、5年の消滅時効になります(民法166条1項1号)。
したがって、遺留分侵害額請求権は、早急に遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をするとともに、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をした結果生じる請求権についても、消滅時効にかからないように、法的手続をとる必要があります。
(2)除斥期間
相続開始から10年で除斥期間にかかります。
相続開始の日が起点になりますので、注意が必要です。
6 遺留分に関する民法改正のポイント
民法改正により、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)は、遺留分侵害額請求権になりました。
遺留分減殺請求権は、行使すると、例えば、不動産については、共有になります。
一方、遺留分侵害額請求権を行使した結果、発生する権利は、金銭債権です。
その結果、遺留分侵害額請求権の場合、権利行使の結果発生した金銭債権について、さらに、消滅時効が問題となりますので、注意が必要です。
その他にも、改正された点はありますが、詳しくは、弁護士までご相談ください。
7 遺留分トラブルは弁護士までご相談ください
(1)遺留分には、消滅時効の制度がある
遺留分には、上記のとおり、消滅時効、除斥期間の規定があります。
適切なタイミングで、法的な手続を行わないと、権利が消滅する可能性があります。
(2)遺留分は、トラブルになりやすい
遺留分侵害額請求を受けた立場からすれば、いったん自己の名義に財産を移転した後、遺言書等があるにもかかわらず、遺留分権利者に対し、遺留分侵害額を支払うことについて、心理的な抵抗を持つ方が少なくないと思います。
また、遺留分侵害額請求については、遺産の評価、具体的な遺留分侵害額の計算など、専門的な知識が求められる場合もあります。
遺留分侵害額請求については、遺留分権利者と、遺留分侵害額請求を受けた方との間で、話し合いで解決せず、調停や訴訟になることも少なくありません。
(3)弁護士にできること
①遺留分侵害額請求の通知
寺部法律事務所では、遺留分侵害額請求のご依頼を受けた場合、配達証明付の内容証明郵便にて、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を記載した書面を相手方に送付することが多いです。
相続関係を確認するための戸籍の調査は、ご依頼を受ければ、弁護士が行います。
遺産の調査については、弁護士がご説明をしながら、ご依頼者の方に書類の取得をお願いしています。
②遺留分侵害額請求の調停
遺留分侵害額請求については、家庭裁判所に調停の申立ができます。
寺部法律事務所では、遺留分侵害額請求調停の手続を取り扱っています。
弁護士は、ご依頼を受けると、調停申立書を作成して、裁判所に提出します。
調停の期日には、弁護士は、ご依頼者の方と一緒に出席し、主に、法的な意見について述べます。
調停手続のなかで、合意に達した場合には、裁判所が調停調書を作成し、手続は、終了します。
③遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求について、調停で合意に達しないときなどには、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
寺部法律事務所では、遺留分侵害額請求訴訟を取り扱っています。
弁護士は、ご依頼を受けると、訴状を作成し、裁判所に提出します。
裁判の期日は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。ただし、尋問期日など、ご依頼者の方にご出席をお願いする場合もあります。
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、ご依頼者の方の主張をまとめた準備書面を作成して、裁判所に提出したり、証拠を提出したりします。
8 まとめ
遺留分に関する個別の事案については、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。